行政不服審査制度
1 行政不服審査制度とは
市が行った処分その他公権力の行使にあたる行為について、不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、市などに対して不服を申し立てることができます。
これは、市民の皆様の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
平成28年4月1日、改正行政不服審査法が施行され、従来よりも簡易・迅速で公正な手続に変更されました。以下、変更後の手続について説明いたします。
2 審査請求
市などに対する不服の申立てを「審査請求」といいます。
(1)審査請求先
- 処分を行った行政庁(処分庁)にとっての再上級庁が、審査庁となり、審査請求先となります。
- ただし、上級庁が存在しない場合は、処分庁に対して審査請求をすることになります。
(2)審査請求をすることができる期間
- 原則として、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
- ただし、処分のあったことを知らなかった場合は、例外として、処分のあった日の翌日から起算してから1年以内は審査請求をすることができます。
(3)審査請求に関する教示
- 市が交付する処分の通知書には、処分について不服がある場合の「審査請求先」や「審査請求をすることができる期間」に関する説明文を掲載しています(または、別紙として説明文を添付しています)。
- それぞれの処分によって、審査請求先などが異なる場合がありますので、詳しくはこれらの説明文をご確認ください。
(4)審査請求書の様式
- 様式は任意ですが、行政不服審査法により、審査請求書に記載しなければならない事項が定められています。
- 参考として、これらの事項をまとめた書面を用意しております。
審査請求書の参考様式は以下のリンクをご覧ください。
3 審理員
- 審査庁は、審査請求を受けた後、審査請求の対象となっている処分に関与していない職員から「審理員」を指名します。
- 審理員は、審査請求人と処分庁(担当部署)の主張を公平に聴取するなどして、処分に違法・不当な点がなかったか、公正・中立に審理を行います。
- 審理手続の終結後、審理員意見書を作成し、審査庁に提出します。
(注意)市長以外の機関(市教育委員会など)が審査庁となる場合は、審理員の指名を行いません。
4 行政手続・行政不服審査会
- 審査庁は、法律の専門家や学識経験者などにより構成される「行政手続・行政不服審査会」に対し、審理員意見書やその他の資料を添えて諮問します。
- 審査会は、審理員による審理手続が適正であったか、審査請求に関する審査庁の判断が妥当であるかなどについて、第三者の立場からチェックします。
- こうした調査審議を経て、審査会としての見解や意見をまとめ、審査庁に答申します。
(注意)審理員を指名しない場合などにおいては、審査会への諮問を行いません。
(注意)情報公開請求や個人情報開示請求に関する審査請求があった場合は、審理員を指名することなく、専門の第三者機関である「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問することとなります。
5 裁決
- 審査庁は、審査請求に対する最終的な結論として「裁決書」を作成し、審査請求人に通知します。
- 裁決の内容は、「却下」「棄却」「認容」のいずれかになります。
6 その他
処分の通知書には、審査請求のほか、裁判所に処分の取消しを求める訴訟を提起することも可能なときは、訴訟の提起に関する説明文も掲載(または添付)しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 文書法制係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4815
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







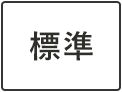
更新日:2023年03月30日