交響詩岩見沢 歌詞解説
歌詞解説 加藤 愛夫 (昭和49年11月2日 披露演奏会プログラムより:原文そのまま)
作詩の構想
岩見沢市開基90年、市制施行30周年を祝して岩見沢賛歌を作詩したいと考え歌詞の構成には、開拓以来の土地の姿を想像し石炭発見と鉄道開設から開拓者入地の歴史をたどり、まちづくり、故郷としての栄光の土地を表現し、北海道の象徴的理想のまちとしての、未来への夢と希望とを織り込み、岩見沢憲章を柱として作詩しました。
序章 コタン
開拓以前の石狩平野の姿を描いたもので、ヌタクカムシュペ(大雪山)から流れ落ちた石狩川は平野を曲がりくねり、肥沃なる密林や沃野を造って石狩湾に注いでいる。
昔アイヌは川口に部落(コタン)を造り、川は生活の場で豊かな魚猟を与えた。食料に恵まれた民族の平和な暮らしは、石狩川の流れと共につづいたことを歌った。
第一章 村の誕生
現在の幌向(ポロ・モイ・ブトは大きな静かな川の出口の意味)附近から石狩川の支流幌向川、幾春別川が渓谷のような密林の中を流れていた。明治6年幾春別川をさかのぼって、ライマンの煤田層調査隊が入り、榎本武揚も調査に入る。翌7年初めて地図上に岩見沢の地名が使われた。
松本十郎大判官も幌内を巡視して、岩のような石炭のあらわれている横の樹をけずり、「盛哉盛哉、皇国第一の宝と謂うべし」としるした由、伝えられる。
明治12年クロフォード技師の測量隊が入り、岩見沢幌向間の道路が開通し、15年には手宮まで開通、岩見沢駅が設置された。将来、交通の要路たらんと言われたという。17年岩見沢村誕生、17年から18年にかけて山口、鳥取県の士族移民をはじめ、10県の移民が入地、はじめて開拓の鍬を下した。
第二章 故郷の栄光
昔は今日のような農機具もなく、設備もなく、木綿の着物で仕事をした。極寒の冬にストーブもなく、風の通過する開拓小屋住まいで士族移民は鍬を使うことも知らなかった。そして、迫る郷愁と闘い、その困苦の惨状は想像以上であった。その中に堪え忍びつつ今日の岩見沢が建設され、祖父達は世を去り、二代三代となり、産業の都市となり、文化香るまちとなった。これは風土の豊かな恵みと交通の良いことが加わって、一層の発展を招いた。この誇りを持って、更に美しいまちづくりを讃えたい。
第三章 北国の象徴
私たちの生活に雪と寒気はつきもので、この気象条件を生活の知恵としてよりよき生活を望む。子供たちは、そこに鍛えられ成長し、雪の下でも蕾を持つ福寿草のように生命を尊び、夢と希望とをもち、あたたかい精神をもって、身障者にも時代の幸福を分かち、ともに愛の心をもって、石狩大平原の中なる北国の象徴であるわたしたちのまちを愛し、未来に向かって常に青春の希望をもつことを大合唱しようではないか。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯教育課 文化・スポーツ振興係
〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢4階
電話:0126-35-5130
ファックス:0126-25-2995
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







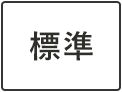
更新日:2022年04月01日