療養の給付
医療機関等にかかったときの自己負担割合
病気やケガをしたときは、医療機関等でマイナ保険証、資格確認書または被保険者証を提示することで、次の一部負担金の割合で保険診療を受けることができます。
| 区分 | 一部負担金の割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学以上70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上(兼高齢受給者証) | 2割(一定の所得がある方(現役並所得者)は3割) |
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保加入者がいる方です。ただし、70歳から74歳の国保加入者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により2割負担となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方がいて現役並み所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保加入者(後期高齢者医療制度に移行する方)も含めた収入合計が520万円未満の方は、申請により2割負担になります。
国民健康保険が使えないとき
病気とみなされないとき
- 人間ドック(健康診断)
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠、分娩
- 経済上の理由による妊娠中絶 など
保険診療の対象とならないとき
- 加入者の希望により保険外診療をした場合
- 入院したときの室料差額(差額ベッド料)
- 歯科診療で特殊材質等を使用した場合の差額診療または自由診療
労災保険の対象となるとき
勤務時間中で業務上のケガや通勤途中のケガ、業務が原因で病気になった場合は、労災保険が適用されるか、労働基準法により雇用主の負担となります。
保険給付が制限されるとき
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ(自殺未遂等も含む)
- 交通事故やけんか、泥酔による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
入院したときの食事代など
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費・居住費を自己負担しますが、住民税非課税世帯、低所得2・1の方は「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請することで、標準負担額を超えた金額については国保が負担します。
制度改正に伴い、令和7年4月診療分より、食事代の標準負担額が変更となります。
入院したときの食事代の標準負担額
| 区分 | 令和6年5月診療分まで | 令和6年6月から令和7年3月診療分 | 令和7年4月診療分から |
|---|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 1食460円 | 1食490円 | 1食510円 |
| 下記以外の指定難病患者または小児慢性特定疾病児童等 または平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病床に入院している方 | 1食260円 | 1食280円 | 1食300円 |
| 住民税非課税世帯・低所得2(過去1年間の入院が90日以内) | 1食210円 | 1食230円 | 1食240円 |
| 住民税非課税世帯・低所得2(過去1年間の入院が91日以上) | 1食160円 | 1食180円 | 1食190円 |
| 低所得1 | 1食100円 | 1食110円 | 1食110円 |
65歳以上の方が療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額
| 区分 | 令和6年5月診療分まで | 令和6年6月から令和7年3月診療分 | 令和7年4月診療分から |
|---|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 1食460円 (一部医療機関では420円) |
1食490円 (一部医療機関では450円) |
1食510円 (一部医療機関では470円) |
| 住民税非課税世帯 | 1食210円 | 1食230円 | 1食240円 |
| 低所得2 | 1食210円 | 1食230円 | 1食240円 |
| 低所得1 | 1食130円 | 1食140円 | 1食140円 |
| 区分 | 居住費 |
|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 1日370円 |
| 住民税非課税世帯 | 1日370円 |
| 低所得2 | 1日370円 |
| 低所得1 | 1日370円 |
- 低所得2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得1を除く)
- 低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得控除は80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
異なる所得区分の標準負担額で支払いをした場合は、食事代の差額を申請することができます。申請については、下記リンクをご確認ください。
医療費を全額自己負担したとき(療養費)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんのでご注意ください。
| 事例 | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 事故や急病で、やむを得ずマイナ保険証、資格確認書または被保険者証を持たずに医療機関等で診療を受けたとき | 資格確認書または被保険者証、マイナンバー、診療内容の明細書、領収書、振込口座の確認ができるもの |
| 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき | 資格確認書または被保険者証、マイナンバー、医師の診断書または意見書、領収書、振込口座の確認ができるもの |
| 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 資格確認書または被保険者証、マイナンバー、明細書がわかる領収書、振込口座の確認ができるもの |
| 手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合) | 資格確認書または被保険者証、マイナンバー、医師の診断書または意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、振込口座の確認ができるもの |
| はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合) | 資格確認書または被保険者証、マイナンバー、医師の同意書、明細がわかる領収書、振込口座の確認ができるもの |
| 海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) | 資格確認書または被保険者証、マイナンバー、診療内容及び領収の明細書(外国語で作成されている場合は翻訳文が必要)、旅券、航空券その他海外に渡航した事実が確認できるもの、現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書、振込口座の確認ができるもの |
- マイナンバーとは、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードのことをいいます。
- マイナンバー通知カードをお持ちの際は、運転免許証等の身分証明書もあわせてお持ちください。
申請書様式のダウンロードや申請方法については、下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







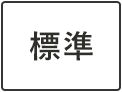
更新日:2026年01月19日