学校の具体的な取り組み
年間計画に基づいた安全教育・安全管理
学校は、「生命の大切さ」を学ぶ安全教育と安全管理を年間指導計画の中に位置付けます。
それに基づき、緊急事態を想定した訓練を実施し、登下校時の安全確保や不審者から身を守る対処法などについて、基礎的、基本的な事項を子どもたちに理解させるよう、具体的な指導を行います。
また、教職員の講習会を実施し、避難経路、避難場所、誘導方法を確認するとともに、防犯用具の使用方法を実際に体験するなど、安全管理意識の高揚を図ります。
安全管理体制の確立
学校は、実際の対応を想定した校内体制を確立します。
- 安全管理マニュアルの理解と周知
- 防犯に関する知識、技能の習得
- 応急手当や心のケア
- 来校者への対応
- 不審者・変質者情報への対応
- 犯行予告、脅迫電話等への対応
施設・設備の点検整備と教職員による校舎内外の巡視
学校の施設・設備の定期的な安全確認や日常的な校舎内外の巡視を全教職員で行います。
- 日常との違いを複数の眼で見る
- 時間や方向を変えて見る
- 安全点検日を設定する
- 点検結果を集約し共有する
登下校時の安全確保
通学路の安全を確保するとともに、定められた通学路により登下校するよう子どもたちを指導します。
- 危険箇所の確認と改善
- 不審者・変質者情報等の確認と対応
- 「子ども110番の家」などの取り組み要請
- 声かけ運動、あいさつ運動、防犯パトロール
- 通学路安全マップの作成
校外での学習活動における安全確保
校外での学習活動では、予想もつかない出来事が起きたり、子どもたちが日ごろとは違う行動をとったりすることがあります。
入念な計画をたて、活動場所および学校からの経路や、非常時の連絡体制の確認など、校外での学習活動中の安全確保を徹底します。
来校者への対応
来校者に対しては、出入口を限定し、受付名簿の記入や職員室・事務室への立ち寄りを求めて、学校内への出入りを把握します。
また、外部指導者や来校予定者については、あらかじめ名簿を作成します。
家庭や地域との密接な連携、協力
家庭、地域住民、関係団体、隣接する学校などと密接に連携し、子どもたちの安全と安心を確保します。
避難訓練や不審者侵入防犯訓練などでは、地域の方にも内容や方法を事前に知らせ、協力を要請します。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







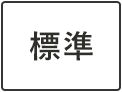
更新日:2022年04月01日